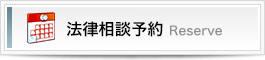他人事ではないことまたは映画「ACT OF KILLING」
話題作である。ついつい見に行ってしまった(4月12日から渋谷のシアターイメージフォーラム他全国で上映http://www.aok-movie.com/theater/)。
内容については下記映画の公式紹介に委ねるとして、考え込んでしまったのは、背景にあるインドネシアの9月30日事件と戦後日本の戦争責任問題との類似性と相違点である。
ここに9月30日事件とは、1965年9月30日でおきたインドネシアのクーデター事件で、指導者がスカルノからスハルトへ権力が交代した。また、スカルノ大統領を支えていたインドネシア共産党が大弾圧を受け、100万人ともいわれる党員や華僑などが虐殺された事件のことである。
9月30日事件後のインドネシアと、程度問題はあるにせよ、戦後日本は無縁ではないように思える。
まず、類似性は、インドネシアも日本も、行った行為についての責任追及が不十分である。
インドネシアでは「共産主義者・華僑」を殺した者達が映画にみるように英雄として顕彰されている。日本でも戦争責任の問題は曖昧にされている。典型的にはA級戦犯は靖国神社に祭られ、A級戦犯であった岸信介は戦後総理大臣になった。戦前、思想犯担当検事で、しかも、治安維持法の立案にあたった池田克は最高裁判事になった(池田判事がどんなに物騒な経歴の持ち主であるかは奥平康弘の「治安維持法小史」(筑摩書房)に詳しい)。
しかし、相違点もある。
流石にインドネシアのように英雄として顕彰されてはいない。不十分ではあるものの多かれ少なかれ戦争責任の追求されている。少なくも、現在、A級戦犯は日陰の存在といっていいだろう。戦前・戦中、国策に反対する「共産主義者」らを弾圧した治安当局者・司法関係者や虐殺行為に荷担した兵士らが積極的に自己の行為を語ることは少ない。岸信介も反省を口にしている。
話は少しそれるが、戦時中、中国戦線おいて百人斬り競争した兵士がいたが、遺族は名誉毀損であるとする裁判を提起されている。当時の英雄として報道された新聞が多数あるにも関わらずである。さすがに名誉毀損は否定された。東京地裁判決2005年8月23日判例時報 最判も上告棄却(ちなみに被告(本多勝一)側代理人の末席に及ばずながら私も連なることができた)
なぜ、インドネシアでは大手を振って歩き、日本では日陰の存在なのか。考えてみると不思議である。
結局、インドネシアの殺人者達は勝者であり、日本の戦争責任者は敗者であることが大きいのだろう。インドネシアでも9:30事件後、殺害行為について責任を問われれば話は違っただろう。しかし、政権担当者は彼らの存在によって自己の権力基盤を築いたのであるために責任追及をすることはできなかった。それどころか、現職の副首相や大臣が登場して殺人者たちを英雄ともてはやす(さすがに、映画において自分は殺害行為など知らなかったというジャーナリストがでてくる。ジャーナリストは、殺人が正当化されないことを知っており、カメラの前で白を切ったと思われる。それを殺人者仲間はそんなことはあり得ないといって難詰する。「颯爽とした」殺人者たちに比べて自分は関係ないと弁解する見苦しい場面であるが、まだ、彼には人の心が残っているのかもしれない)。
恐ろしい話であるが、(太平洋戦争の開戦を決めた重臣達が考えていたように)アメリカには勝てないとしても、適当な時期に休戦を申し込み和平にしてしまえば、日本は負けなかったかもしれない。少なくとも東京裁判はなかっただろう。そうすると戦争責任に対する評価はがらりと変わったかもしれない。大日本国憲法は生き残り、教育勅語も健在で、植民地も存続していたかもしれない。インドネシアの出来事は他人事ではない。
仮に日本が戦争に負けなかったとしたら、民主化に成功していただろうか。随分と困難な道ではないだろうか。その点で参考になるのは戦後のスペインである。ファシズム国家のフランコ体制は戦後も生き延びたが、長い時間をかけて次第に民主化することに成功した(山森良一)。
以下、映画の紹介文である(http://aok-movie.com/)。
これが“悪の正体”なのか―――。60年代のインドネシアで密かに行われた100万人規模の大虐殺。その実行者たちは、驚くべきことに、いまも“国民的英雄”として楽しげに暮らしている。映画作家ジョシュア・オッペンハイマーは人権団体の依頼で虐殺の被害者を取材していたが、当局から被害者への接触を禁止され、対象を加害者に変更。彼らが嬉々として過去の行為を再現して見せたのをきっかけに、「では、あなたたち自身で、カメラの前で演じてみませんか」と持ちかけてみた。まるで映画スター気取りで、身振り手振りで殺人の様子を詳細に演じてみせる男たち。しかし、その再演は、彼らにある変化をもたらしていく…。