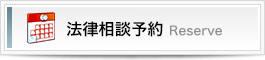靖国神社とアンティゴネーの対比
今月号の文芸春秋が面白かった。例えば、石原慎太郎がテロリスト山口二矢を褒めたたたえていることに驚嘆した。以前、9月30日事件で100万人の共産党員や華僑を殺したテロリストが英雄になっているインドネシアを描いた「アクトオブキリング」を紹介したが、石原のような人間が平然としてられる日本はインドネシアとあまり変わらない。
それはともかく、面白かったのは井上章一の靖国神社論である。
靖国神社は政権のために戦ってなくなった人々の霊を慰める施設である。幕府の側で戦った者は祭られない。西南戦争の西郷軍や226事件の反乱兵も祭られない。政権がけちらしてきた側は一瞥もくれない施設である。これに対して、井上は、時の政権によって滅ぼされた側の魂を鎮める役割を果たしてきた伝統的な御霊会を対置する(文藝春秋6月号295p)。このように御霊会と対比して考えると、死者を祭ることについて靖国神社は狭い考えにもとづいた施設であることがわかる。否、むしろ国家のための尽くした人だけを祭るということで靖国神社は合理的で純化した施設というべきか。
そこで思い出されるのはギリシャ悲劇「アンティゴネー」である。周知のようにアンティゴネーの父オイデプスは、自分が父親を殺し、母親を妻としていたことを知り絶望し、自分の目をくり貫き諸国を放浪した末死ぬ。残された息子たちは統治の主導権を争い、兄は戦死する。兄は反逆者として国法上埋葬は許されず野ざらしになる。これを妹のアンティゴネーがみていられず兄を葬る。アンティゴネーは肉親への情、人倫を優先し敢えて国法を無視する。肉親の死を悼む生者の想いとはこういったものであろう。時の国王クレオンは姪のアンティゴネーを死刑に処す。殺されるとわかっていても死者を悼む気持ちはやみがたいものであるのだろう。それは古代ギリシャ人であろうが、日本人であろうが、中国人であろうがインドネシア人であろうが変わらないだろう。
靖国神社とアンティゴネーはあまり関係ないかもしれないが、以下のような対比をすることはできないだろうか。
靖国神社は死者一般に対する悼みのうち、日本のために戦って死んだ人だけを悼むという限定を付ける。
アンティゴネーの場合、死者一般のうち、国法で許された者についてのみ悼むという限定を付けた国王(クレオン)に対して、アンティゴネーは命をかけてその限定を破る。靖国神社は悼む者を国家のためということで限定しようとする。アンティゴネーは悼むために国家の枠を取り払う。
アジア太平洋戦争で死んだ日本人を肉親が悼むのは当然のことである。それは中国人だろうが、韓国人であろうがおなじことである。しかし、靖国神社の場合、日本人(旧植民地の日本人も含む(靖国神社の解説))で日本のために死んだというフィルターを掛ける。
しかし、日本人以外の死者に対してどうしてかくも無関心でいられるのか。また、日本人の死者の中でも賊軍といわれ死んでいった人に対して一顧だにしないというのはどういうことか。
日本人であれ、中国人であれ、フィリピン人であれ、賊軍であれ、戦争や内乱で死んだ人々の魂を慰霊するというのが、生者の通常の気持ちではないだろうか。
靖国神社は日本国家のために死んだ人を顕彰するという点では合理的であるが、死者に対する慰霊という観点からみると狭量である。私はアンティゴネーを尊敬する(山森)